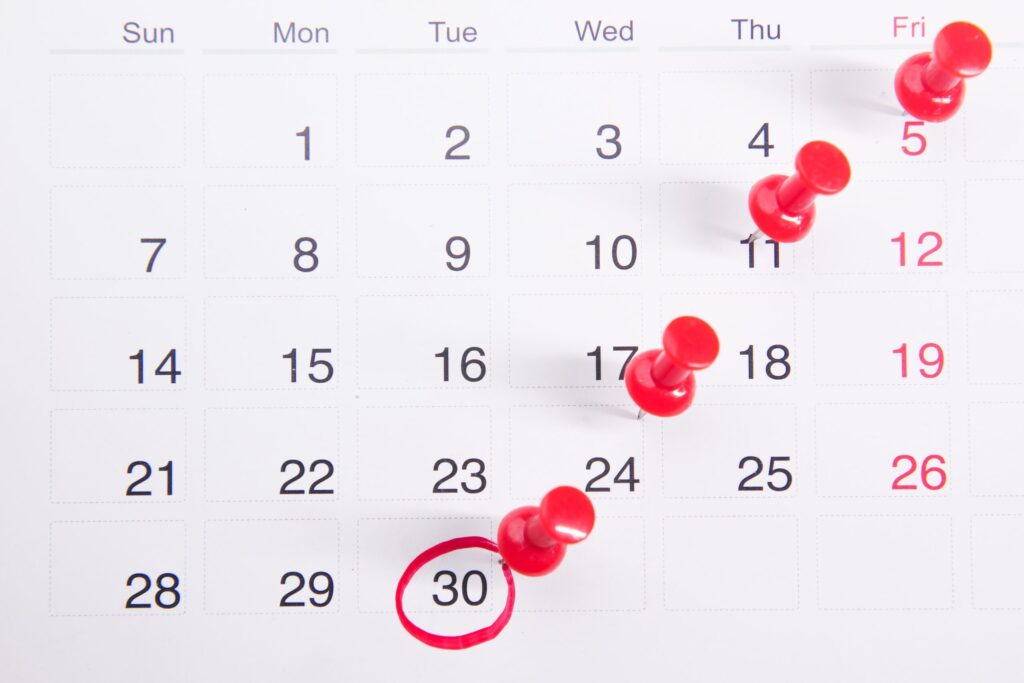この記事では消費税のインボイス制度がいつから始まるのか、また登録申請をいつまでにすればいいのか解説していきます。
結論から言うと令和5年(2023年)10月1日から制度が始まり、原則として令和5年3月31日までに申請が必要です。
インボイス制度に登録をしないと、課税事業者の場合は仕入税額控除が受けられず、消費税の納付額が増えてしまいます。
免税事業者であっても、登録しないとインボイスの発行ができないという点に注意が必要です。
「免税事業者だから消費税は関係ない。」と決めつけてしまうと、思いがけない問題が出てくる可能性があります。
個人事業主は特に気を付けてください。
まずは確認!インボイス制度の概要について簡単に解説!

まずはインボイス制度について簡単に確認しておきましょう。
- インボイス制度⇒「適格請求書保存方式」とも呼ばれる。
- 「適格請求書」(インボイス)とは、登録番号などの記載要件を満たした請求書のこと。
- インボイス制度の登録番号を取得するには、税務署に申請し登録事業者になる必要がある。
- 仕入税額控除を受けるためには、インボイスの発行と保存が必要になる。
- インボイスを発行するのにも登録が必要。
インボイス制度は「適格請求書等保存方式」とも呼ばれ、消費税の申告にかかわる制度です。
日本では現在、消費税率10%と8%が混在しており、仕入と販売で税率に差が出るケースがあります。
この複数税率により起こる計算ミスや、不正を防止するためにインボイス制度の導入が決定されました。
インボイス制度についてもっと詳しく確認したいという方は、以下の国税庁HPをご参照ください。
消費税のインボイス制度は令和5年の10月から開始します!

インボイス制度の開始時期は、令和5年(2023年)10月1日からです。
開始時期については、平成28年度税制改正大網で、2021年4月1日から2023年10月1日に延期されて以降変更はありません。
また、2019年10月~2023年9月までが準備期間として設けられています。
「準備期間?」と思う方もいるかもしれませんので、その期間にするべきことを挙げてみます。
- 税務署に「適格請求書発行事業者」の登録申請
- 免税事業者の場合、課税事業者になることを検討する
- 「適格請求書」(インボイス)の発行準備やシステムなどの整備
なぜ免税事業者なのに、わざわざ課税事業者になることを検討するのかというと、免税事業者はインボイス制度に登録ができないからです。
インボイス制度に登録できないと、インボイスの発行ができません。
インボイスの発行ができないと、取引先が課税事業者の場合、その取引先は仕入税額控除を受けられなくなってしまいます。
仕入税額控除を受けるにはインボイスの保存が必要だからです。
よって現在、免税事業者であっても取引先の状況をよく調査し、場合によっては課税事業者になることも検討してください。
消費税のインボイス制度の申請の期限はいつまで?
インボイス制度開始からすぐに対応できるようにするには、令和5年(2023年)3月31日までに税務署に「適格請求書発行事業者」の登録申請が必要です。
| 申請者の状況 | 期限 |
| 原則 | 令和5年3月31日 |
| 困難な事情がある場合 | 令和5年9月30日 |
ただし、期限が近付くと駆け込みが予想され、確定申告の時期でもあるので税務署の混雑が予想されます。
そのため、登録申請は余裕をもって、早めにした方が良いでしょう。
消費税のインボイス制度の登録申請書の提出方法
- e-Taxによる登録申請手続き
- 郵送による登録申請手続き
インボイス制度では、登録申請書の提出方法が主に2通りあります。
所轄の税務署に登録申請書を提出し、審査を経て適格請求書発行事業者に登録されるという流れになります。
詳しい方法や登録申請ページ、申請書のダウンロードについても国税庁のHPにあるので、ご参照ください。
消費税のインボイス制度の対応が必要な人と提出時期
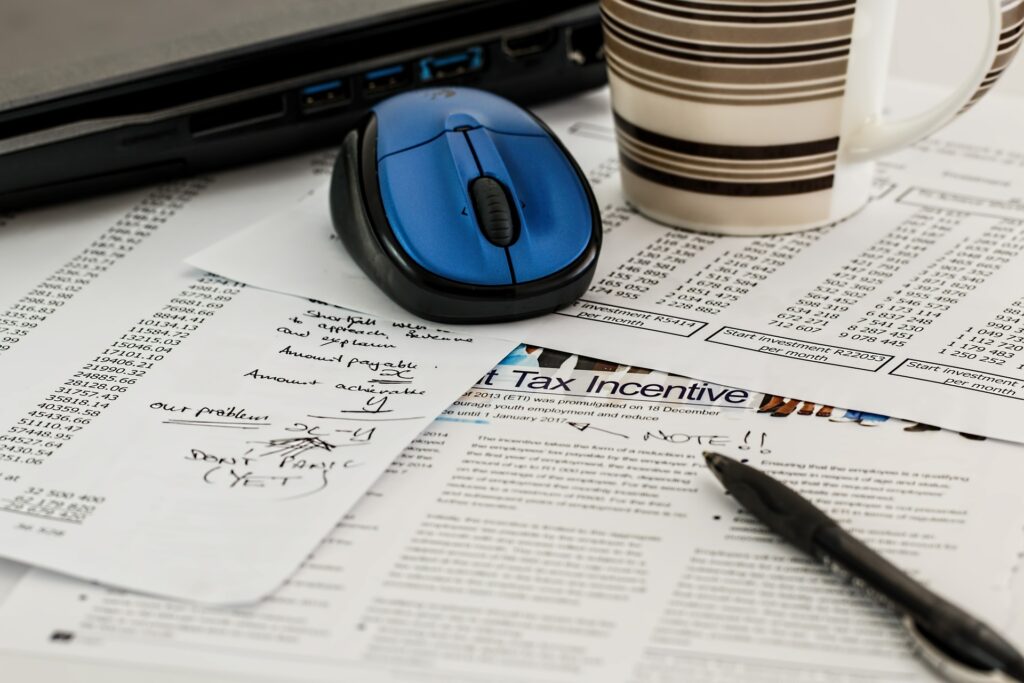
先ほども述べましたが、インボイス制度は令和5年(2023年)3月31日までに申請が必要です。
課税事業者の場合は、仕入税額控除を受けられないという明らかなデメリットがあるので、ほとんどの事業者が期日までに登録すると思います。
よく考える必要があるは、免税事業者の場合です。
インボイス制度が始まっても「売上1,000万円以下であれば免税事業者」というのは変わりません。
しかし、先に述べたようにインボイス制度に登録申請をしないと、「インボイスの発行ができない」という点に注意が必要です。
取引先が課税事業者だった場合、インボイスが発行できない取引に関しては仕入税額控除が使えません。
つまり課税事業者の取引先からみると、同じ内容の取引であれば、インボイスを発行できる業者と取引をした方が消費税を抑えられるということです。
結果的にインボイスを発行できないことを理由に、取引を他社に回されてしまう可能性も生じてしまいます。
免税事業者の場合は特に、取引先がインボイスを必要としているかを事前に調査して、判断していきましょう。
インボイス制度の申請が必要な人①:個人事業主(免税事業者)
冒頭でも話しましたが、免税事業者の場合、取引先の状況をよく調査して検討しましょう。
例えば以下にあげるような事業をしている場合、インボイス制度への登録申請が必要になる可能性があります。
【インボイス制度の対応が必要な人の例】
- フリーランスで企業向けに売上がある(Webデザイナー、Webライター、プログラマーなど)
- 飲食業(企業が接待等で使う場合)
- 企業に出向いて、英会話講師などをしている。
- 書類作成代行
- その他企業向けに技術提供や売上がある
上記のように、企業向けに取引がある場合、インボイスを要求されることが出てくるでしょう。
逆に理髪店やマッサージ店、子供向けの学習塾など一般消費者向けしかない場合や、取引先が免税事業者しかない場合などは登録しなくても問題ないかもしれません。
まとめると個人事業者(免税事業者)は以下のフローでインボイス制度に備えると良いでしょう。
- 主要な取引先が課税事業者か?
[yes]→2.以降の手順で対応
[No] →取引先が免税事業者や一般消費者、非課税取引が多い場合は免税事業者のまま。 - 「消費税課税事業者選択届出書」を所轄の税務署に提出する。
- 「適格請求書発行事業者」の登録申請をする。
- インボイス制度に対応した請求書のフォーマットや取引を記録するツール等の準備
もちろん課税事業者へ変更した場合、今までなかった消費税の申告と納税義務が発生します。
令和5年3月31日までにインボイス制度への申請を済ませ、消費税納税への準備もあわせて進めていきましょう。
インボイス制度の申請が必要な人②:法人(免税事業者)
免税事業者の法人も個人事業主と同様に、取引先がインボイスを必要としているかを基準に、インボイス制度へ申請するかを判断しましょう。
企業対企業(B to B)のビジネスを行っている場合、多くのケースでインボイス制度の対応が必要になると思われます。
逆に不要と考えられるのは、以下のケースです。
- 取り扱っている商品が非課税
- 乗り換えられるライバルがいない
例えば、居住用の家賃や保険診療などが売り上げの場合は、そもそも消費税がかからないので、インボイスを要求されることはないでしょう。
多少強引な気もしますが、乗り換えられるライバルがいないのであれば、免税事業者のままという選択肢もありです。
インボイス制度の申請が必要な人③:個人と法人(課税事業者)
課税事業者の場合は、個人でも法人でもインボイス制度の申請をした方がよいでしょう。
なぜならインボイス制度に登録しないと、仕入税額控除そのものを受けられなくなってしまうからです。
少し本題からそれますが、気を付けておきたいのは、仕入先が免税事業者である場合です。
インボイス制度では、仕入税額控除を受けるためにはインボイスの保存が必要です。
しかし、免税事業者はインボイスの発行ができません。
つまり免税事業者からの仕入があると、インボイスがないためその分は仕入税額控除を受けられず、消費税負担が多くなってしまいます。
そのため、仕入先に課税事業者になってもらう、あるいは消費税分割り引いた価格で取引できないかなど、事前に取り決めておく事をおすすめします。
消費税のインボイス制度の開始時期やいつまでに申請書が必要かのまとめ

| インボイス制度 | 時期・期限 |
| 開始時期 | 2023年(令和5年)10月1日から |
| 登録期限 | 2023年(令和5年)3月31日まで |
インボイス制度の開始時期と期限には十分注意してください。
また、課税事業者か免税事業者かによって登録申請で考えるポイントが異なります。
- 課税事業者の場合:仕入税額控除を受けられなくなるので、期限までに申請し、準備を進めていきましょう。
- 免税事業者の場合:取引先がインボイスを必要としているかをよく調査して、準備していきましょう。
免税事業者はインボイス制度に登録ができないので、インボイスの発行ができません。
そのため取引先がインボイスを必要としている場合、課税事業者への変更を検討する必要があります。
登録期限まではまだ少し時間がありますので、取引先とも十分に話し合って判断していきましょう。
以上、ぜひ参考にしてください。